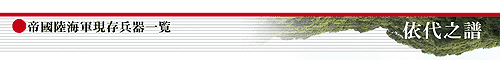佐賀城本丸歴史館 佐賀/佐賀
- モルチール砲
- アームストロング砲(レプリカ)
- 24ポンド加農砲(レプリカ)
|
|
|
幕末期の本丸御殿を復元したもので、平成16年に開館。
|
|
|
|
▲上から、スタール騎銃(後装・施条)、ウェストリー・リチャード銃(後装・施条)、エンフィールド銃(前装・施条)、エンフィールド銃(前装・施条)、ゲベール銃(前装・滑腔)、火縄銃(前装・滑腔) |
|
|
|
▲砲身をくり抜く鑽開台の模型。動力は水車から。 |
|
|
 |
 |
|
▲モルチール砲・青銅製29拇砲 左:「冠軍」「蓮池」の銘。蓮池藩は佐賀藩の支藩のひとつ。 |
 |
▲24ポンド加農砲・鋳鉄二四斤加農のレプリカ 大正十五年五月に、旧佐賀藩の鍋島直映侯爵から海軍宛に下附願が出され、「鉄製二十四封度砲」二門と「鉄製後装アムストロング砲」二門 を受領している。 ところで、この説明板には |
 |
▲これは戸栗美術館(元は鍋島邸の一部)の24ポンド加農砲 上記の砲の下附には佐賀藩出身の秀島成忠少将の根回しがあった。同時期、秀島少将は予備役となり、藩主の鍋島直映公から佐賀藩の銃砲に関する沿革の調査・編纂の依頼を受けていた。 |
 |
| ▲『佐賀藩銃砲沿革史』から |
 |
 |
▲アームストロング砲のレプリカ 大正十五年に下附された「鉄製後装アムストロング砲 二門」 は 下附されたアームストロング砲二門は築地の水交社で廃砲の中から発見したもので、下附を受けたあとは佐賀徴古館前と渋谷鍋島邸に置かれていた。双方とも後装施條砲だが尾栓の型式が異なる別種だった。 |
.H20.5.29