.
貴布禰神社 千葉/富津
- 砲弾
|
|
|
境内の碑に、「貴布禰神社は弟橘媛命を奉斎し
|
| 日本武尊が東征の際、走水(横須賀)から船出して上総国へ向かったが、大風により難船しそうになった。そのとき、お伴していた妃の弟橘媛が海神を鎮めようと入水、大波は鎮まり日本式尊は上総国へ上陸することができた。 そして富津岬の布引海岸に弟橘媛が身につけていた衣が流れ着き、布流津(富津市)の由来となったという。 |
| 境内に奉納された砲弾が置かれている。 |
 |
 |
|
▲砲弾 径:約407ミリ、長:約1380ミリ |
 |
 |
| ▲試製四十一糎榴弾砲 破甲榴弾 弾体に刻字 「奉」「納」 台坐のプレート 「潜水業者一同」 |
.
.
富津には砲台があったが大正8年に整理除籍となり、その後は陸軍火砲の試験射場となっていた。 試験射撃の結果は良好だったが、海軍軍縮で余剰となった艦載砲が陸軍で海岸砲として使用されることになり、「試製四十一糎榴弾砲」は富津で格納されたまま放置された。
|
|
| 貴布禰神社は旧富津射場敷地に隣接している。 房総は明治初期から、潜水器・潜水服による潜水漁法が盛んで、主に貝類を採取、業者は漁業だけではなく海底の調査や工事、沈船や墜落機の捜索・回収など、軍や民間からのさまざまな要請にも応えていた。 昭和二十年の日本の敗戦で日本軍は占領軍が来る前に武器・弾薬を近海に投棄したのだが、昭和二十五年に朝鮮戦争が勃発すると金属類が高く売れるようになった。 東京湾、とくに富津周辺の海は軍の投棄物が豊富で、業者は本業そっちのけで金属類の水揚げに励んだ。この特需は二、三年続き、豊漁の記念にこの砲弾が貴布禰神社に奉納されたものと思われる。 |
R3.5.9
.
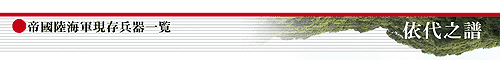

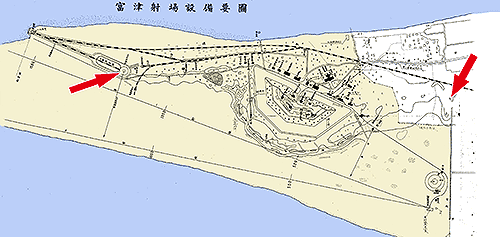 ▲富津射場設備要図(昭14)
▲富津射場設備要図(昭14)